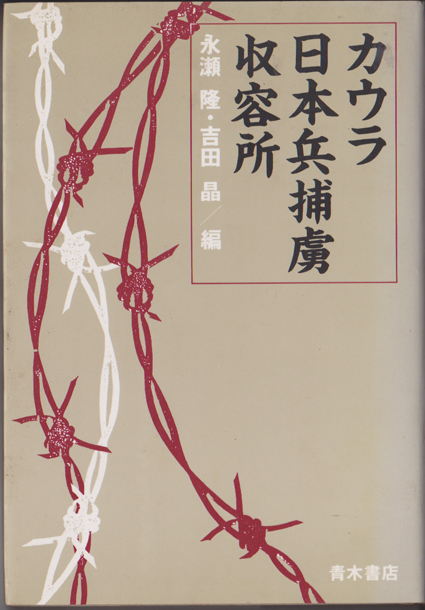 |
| 10-12000 |
|---|
 |
| 10-12001 2019 12 9 四国新聞 より |
|
『カウラ日本兵捕虜収容所』”永瀬 隆、吉田 晶 編 青木書店より
序章 カウラ事件とカウラ収容所 五十嵐 武 カウラ事件とはどのような事件だったのか、なぜこのような脱走事件が引き起こされたのか、この事件の持つ意味などを、生存者の証言、オーストラリア側での日本軍捕虜の遺体確認 にあたったジャック・リーマン中尉の著書『幸福な墓堀り』、オーストラリアの軍事報告書、カウラ事件の研究者オーストラリア国立大学教授シソンズ氏の研究などを参考にして明らかに したい。 事件は太平洋戦争の末期、1944年(昭和19)8月5日午前1時50分ごろ起こった。オーストラリア、ニューサウスウェールズ州のカウラ第12捕虜収容所の日本人捕虜が引き起 こした集団脱走事件である。カウラ捕虜収容所はカウラの町から北に3キロほど行った丘の向こう側にあった。ゆるやかな山の斜面を切り開いてつくられ、12面の多角形をしていた。 直径約650mの十字形の菓子パンのような形で、4つのコンパウンド(地区)に分けられていた。1つのコンパウンドは約7haあった。外側とは三重の高さ約2mの鉄条網つきフェンス で仕切られていた。 コーナーには約6mの高さの監視塔があり、小銃を持った監視兵がいた。また多角形の敷地の最外側は柵にそった巡回区域で、軽機関銃を持った監視兵が配置されていた。当時、同収容所 には日本軍将校・下士官・兵とイタリア人捕虜などが収容されていたが、事件はB地区に収容されていた日本軍下士官・兵、1104名によって引き起こされた。この集団脱走事件の結果、 日本人将兵231名が死亡し(シソンズ氏によれば、のちの死亡者を含め234名)、負傷者は105名であった。オーストラリア軍も死者4名、負傷者4名の被害者を出した。 さて、この事件の背景は何だったのか。8月5日の事件にいたる経過をみていく。 日本ではほとんど知られていないが、すでにこの事件の前年、1943年(昭和18)2月に、ニュージーランドのフェザストン収容所でも、約300名の日本人捕虜の強硬分子が「将校たち に自決することで指導権を示せと要求し、将校たちが拒否すると彼らを脅かした」。そして、こうしたトラブルが捕虜たちのストライキに発展し、フェザンストン収容所の武装警備隊と乱闘・ 一斉射撃にいきつく。このフェザストン事件では、日本兵死亡48名、負傷者61名、ニュージーランド側は死亡1名、負傷者17名を出した。(シソンズ証言および同氏の「カウラ捕虜 キャンプの反乱」『歴史と人物』165号、1984年所収)。 太平洋戦争も1944年(昭和19)ごろには、南太平洋での度重なる敗戦からオーストラリア内での日本人捕虜の数は増加の一途をたどっていた。ちなみに日本人捕虜は1942年 (昭和17)末には10名だったものが、1943年11月末には456名、事件直前の1944年7月1日には1415名に達していた(シソンズ証言)。カウラ収容所の日本人捕虜 の数も増加し、オーストラリア軍は収容所の地区ごとの日本人捕虜の人数を減らす指令を6月19日に出した。すなわち6月19日現在、B地区には下士官と一般兵士779名が収容され ていたが、B地区は下士官のみにして、一般兵士をさらに奥地にあるヘイ収容所に移動させるというものだった。8月4日の朝、オーストラリア軍の司令官から移動が指示された。出発は 翌8月5日だから準備をしておくようにということで、移動リストも渡された。 この移動問題をめぐって班長会議がくりかえされた。班長会議は紛糾し、そのため移動の指示に従うか否かを全員の投票によって決定することにした。捕虜たちの間では移動を拒否して 決起すべきだという意見が強まった。決起とは収容所からの集団脱走=出撃である。この出撃に賛成か反対かを〇×で投票用紙に記入していった。〇と記入することは死を、×と記入する ことは生を意味していた。班員の心のなかでは生死をめぐって激しい葛藤が続き、身をよじるような思いであったに違いない。後述の生存者の証言がそのときの心情を生々しく伝えている。 〇(出撃に賛成)を決断させた力は戦陣訓の一節の絶対的な重みでった。「恥を知る者は強し。……生きて虜囚の辱め(はずかしめ)を受けず、死して罪過(ざいか)の汚名を残すこと勿 れ(なかれ)……」強硬派の人びとだけでなく、すべての日本人がこれに縛られていた。一方、×(出撃に反対)を決断させた力は人間であるかぎり誰しももっている「生への執着」で あった。たとえようのない苦悩が日本人捕虜を追い詰めていった。しかし決断しなければならなかった。投票がおこなわれた。開票の結果、「80%が〇、20%が×だった」との報告 により集団脱走が決定された(この開票結果については、開票の経過が非公開であったため、生存者のなかには疑問視するものもある)8月4日の深夜24時ごろであった。この結果は ただちに全員に伝えられ、脱走の時刻は8月5日午前2時と決定された。 こうして8月5日、午前1時50分、収容所のB地区において無許可の突撃ラッパが鳴りひびき、その直後900名以上の捕虜は、生活していた20余りの棟小屋(ハット)から喊声 をあげて脱走を計った。」捕虜は脱走に先立って小屋に放火した。脱走は3か所からおこなわれた。主部隊は200名と300名に分かれ、収容所と外側を隔てるバリケードを2か所 から突破しようとした。バリケードを超えるために野球用のグローブ、手袋、タオルなどを持ち、毛布を鉄条網に架けて脱出を図った。また捕虜はオーストラリア兵襲撃のため料理用 包丁、野球用バット、棍棒などで武装していた。他の一団は200〜250名がB地区のゲートおよび内部道路(ブロードウェイ)との間の柵を乗り越え、内部道路から南北の門を突破 しようとした。彼らは2グループに分かれ、一方は北側の門を突破して敵兵舎を襲撃しようとした。他方はD地区に侵入し、朝鮮、台湾人捕虜のいる地区の門や日本人将校捕虜の地区 の門を開かせた。 これらの襲撃の結末を見てみよう。まず収容所の外へ脱出した一団の一部は北側のオーストラリア兵の兵舎を襲撃したが失敗し、他の一団も収容所南側の兵舎を襲撃したが、失敗した。 収容所外へ脱走した残り70名は収容所を見下ろす丘の上に集結していたが、朝になって拘引された。そのほか何名かが外部へ脱走し、のちに付近の農家に食糧などを求めに姿を現わし 最終的には連れ戻された。内部道路を突破した一隊の南北の門への攻撃はオーストラリア兵の抵抗で失敗し、一部の捕虜は朝まで道路の側溝に隠れていたところを連れ戻された。この グループのなかのもう一方の一団は日本軍将校が収容されいたD地区に押し寄せ、約50名が、朝逮捕されるまで潜んでいた。こうして集団脱走は失敗に終わった。 犠牲者について述べておこう。日本人は231名が死亡し、負傷者は105名にのぼった。資料で分かっているものだけであるが死者の死因を述べると、小屋の中で焼死したり縊死し た者20名、収容所外側の柵で死亡していた者44名、事件後収容所周辺で発見されていた者25名で、その25名は縊死したり、携行したナイフで刺殺した形跡があった。このように この集団脱走が生き延びるためのものではなかったことは明らかである。また、この集団脱走事件には日本人将校が協力し、5人の日本人将校が収容所B地区の捕虜団長=金沢曹長に、 事件についての尋問で陳述する点についてあらかじめ指示していた。一方、オーストラリア側は第2号ヴィカース機関銃の守備兵2名ほか計4名が死亡し、4名が負傷した。 このような集団脱走事件がなぜ起きたか。生存者の証言、軍事法廷の報告書によっても、捕虜の待遇が劣悪だったという指摘は皆無である。それどころか捕虜の処遇は極めて良好だった と証言している。元カウラ会会長の故・堂市次郎氏によれば以下のような処遇であったという。 (プリスベーン陸軍病院での)生活は、朝3時に検温、ただちにお湯で全身を拭き、パジャマ、シーツ、毛布おおいなど全部取り替えて仮眠。6時半に朝食、9時ドクター回診、10時 ティータイム、5時半夕食、9時夜食というものであった。これが昭和18年2月中の日本兵捕虜に対する扱いだった。……(カウラ収容所での)豪兵は(燃料用の薪取り)作業の能率 等は喧しく言わず、自由に任せていたようで、毎日ピクニックに行く如くで、志願者が多く班長も人選に困る位で、余分に割り込まれるので手を焼いていたものだ。……食糧も充分あり、 ビスケットは食べきれずに全部ストーブで焼却した。日本の食糧不足を思えば、もったいないことであった。日本人は米食だから、米を支給させ、魚をよこせといえばニュージーランド から輸入して支給してくれた(常市次郎「カウラ捕虜収容所脱出事件」『新評』1972年8月号所収)。 また生存者の1人である高原希国民氏は自著『カウラ物語』のなかで、米、羊肉、魚、牛乳、玉ねぎやジャガイモなどの野菜がふんだんに支給され、<最高の食事情>だったと表現し ている。その他シソンズ教授の証言やオーストラリア軍の軍事法廷査問委員会の報告書によっても、捕虜が不法に虐待された事実はいっさい見られないし、捕虜は軍事法廷で不法に殺害 された事実がないかとうか確かめる権利も保証されていたという。 それではいったいどうして集団脱走を試みたのか。 第二次大戦中、オーストラリアに留置された捕虜はイタリア人1万8164人、日本人5103人、ドイツ人1492人で、ドイツ人全員とイタリア人の半分以上は日本との戦争突入 までに到着していた。日本人捕虜は最新参者だった。これらの捕虜のうち、イタリア人捕虜はオーストラリア軍に対しほとんど敵意を見せなかったのに対し、日本人捕虜は敵意に満ち 残忍性があると見なされていた。 このような日本人捕虜のなかにあった敵対意識がカウラ事件の遠因になっていた。事件は偶発的に起こったのではない。すでに、1944年6月3日、カウラ捕虜収容所の朝鮮人 捕虜がオーストラリア軍の通訳に、日本人捕虜のなかで反乱計画がひそかに進行しているのを聞いたと伝えてきている(シソンズ氏前掲論文)。やはり日本人で「捕虜」になったという 戦陣訓の道徳観以外には考えられない。捕虜には「死」という道しか残されていなかったといえよう。これは捕虜の生存者を戦後も長いあいだ呪縛しつづけてきた。生存者のなかには 捕虜であったことを語ることができなかった人びともすくなくなかったのである。私たちがカウラ事件を掘り起こすことになったのもこの事実にぶつかったからにほかならない。 |
|
次のページに進むには次の矢印をクリック → トップページにもどるには次の矢印をクリック → |