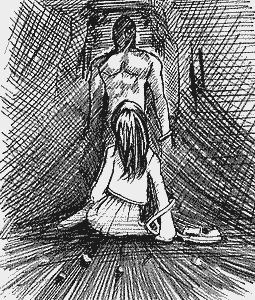
*
その日、彼女――ヒルデ・ハイデンベルクは夕闇迫る黒い森を歩いていた。
彼女の住む街から車で二十分以上掛かる郊外のこの森の中には、彼女のピアノの教師が住んでいる。
教師は非常に気まぐれな性格で、ヒルデがピアノを始めた時
彼はヒルデの自宅の近所に居を構えていた。
もともと彼は非常に高名なピアニストであったらしく、家も近所であるという事からヒルデは彼の元に通うことにしたのだ。
しかし3年程経ったある日、彼は突然郊外のシュバルツバルト(黒い森の意)に
居を移すと言い出し、その後間もなくこの森に引っ越してしまった。
ヒルデとしてはそれを機に教室を変えても良かったのだが、両親が彼をいたく気に入っており、
車で数十分の距離であったことからそのままこの森まで週一回通うことになってしまったのだ。
日増しに気温は低くなり、夜は早まり、季節は冬を迎えようとしていた。
(まいったなぁ、もう暗くなってきたし・・・)
ヒルデは不安そうな顔を浮かべ、森の入り口へ急いだ。いつも彼女の父親は森の入り口で彼女を降ろす。
車ではそれ以上森の中へ入ることができないからだ。お陰で彼女は、森の入り口から教室まで、
約四kmの道のりを歩かなくてはならないのだった。
彼女はこの森が嫌いだった。なぜならこの森は、町でも怪談の舞台として有名だからだ。
ある人はこの森で大きな異形の影を見たと言い、またある人は真っ白な女の姿を見たと言う。
嘘か真かはわからなかったが、その手の話が全く苦手なヒルデを怯えさせるには、その噂は十分だった。
今は黄昏時。次第に辺りが薄暗くなり、自分の足元さえも薄闇の中へ溶けて行くようだった。
(い、急がなきゃ・・・)
出口までは後一キロメートルもないはずだ。
そう思う彼女の足取りが次第に速くなり始めたとき、不意に彼女の耳にある音が飛び込んできた。
――ガサッ
「ひっ・・・!」
草の擦れる音がやけに大きく辺りに響いた。
彼女が既に怯えきった眼で辺りを見回す。その目尻には涙が浮かんでいる。
今日は風が全くない。なにかの動物が通った時の音にしてはその音は大きかったような気がする。
「な、何?」
今にも叫びそうな顔で、来た道を振り返る。しかしそこには何もいない。
既に夜の帳が降り始めた森は、耳が痛くなるほどの静寂を保っていた。
全く音が聞こえない。
(そうよ、きっと物凄く大きな鼠でも通ったのよ。そうだ、そのせいで妙に大きく聞こえただけなんだ。)
その想像もかなり恐いものがあったが、彼女は無理にそう言い聞かせて走り出そうとする。
――そして・・・。
ドンッ
「きゃっ!!」
振り返った彼女の視界が突然真っ暗になったかと思うと、何か壁のようなものに激突して彼女はその場に尻餅をつく。
「い、いったたた・・・。」
彼女はしたたかに打ちつけた腰と鼻とを擦りながら涙を浮かべる。どうやら突然何かに激突して、鼻をぶつけてしまったようだ。
「もぅ、何なのよぅ・・・。」
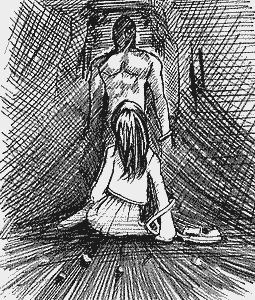
怪訝に思っておもむろに顔を上げたヒルデは今度こそその場で凍りついた。
そこには一人の男が立っていた。
奇妙なことに男は何故か上半身裸であった。その体は彫刻品のように美しく整っていた。
殆ど無駄のない良質の筋肉がつき過ぎることなく全身を覆っていることが、一目でわかった。
しかしその全身は、擦過傷や打撲傷で痛々しいほどに傷ついていた。
そして彼の両腕両足には大きな金属製の腕輪――鎖のようなものが途中で切れてぶら下がっているところを見ると、
恐らくそれは手錠のようなものであろう――が取り付けられている。
男は虚ろな表情で焦点の合っていない目をヒルデに向ける。殆どスキンヘッドに近いくらい短く刈り込んだ頭が、彼の整った眉目とは不釣合いだった。
「ひっ・・・ひっ・・・!」
しかし完全に気が動転しているヒルデにはそんな所にまで気を配る余裕はなかった。
彼女は殆ど恐慌状態に近い程であった。男がそんな彼女を向いて苦しげに眉をひそめる。
「あ・・・ぁう・・・。」
彼の口が紡いだのはそれだけだった。急に糸が切れたように彼はその場に膝をつき、
ヒルデに覆い被さるようにその場に崩れ落ちた。
その巨躯を受け止めて、否、受け止められずその場に押し倒されるように倒れこんで、ヒルデは思い切り息を吸い込んだ。
きゃああぁあああぁぁあぁぁあああぁあぁぁ!!!
シュバルツバルトの夜空にヒルデの絶叫がこだました。
「記憶喪失ぅ!?」
放課後の活気にざわめき出した食堂に、一際大きな声が上がった。
帰る前に腹ごしらえをして行こうという生徒がまばらにいる中、
端の方に座っている二人の女の子の一人が上げた声だった。
利発そうな外見そのままの、よく通る声音だ。
彼女は長い栗色の髪にピンク色のカチューシャがよく似合う、
面立ちに幼さを残した可愛らしい女の子だった。
体形には一切の無駄はなく、服の上からでもわかる程に
非常に均整の取れたバランスの良い肢体だ。
彼女が着ているブルゾンの背中の、鷲を象ったエンブレムが大げさに揺れる。
「じゃあその人、なにかの事故に巻き込まれたって事?」
彼女は興味深そうに大きな瞳を瞬かせ、向かいに座る少女、ヒルデに顔を寄せる。
ヒルデは彼女の大声が恥ずかしかったのか、しきりに周りを気にしながら頷く。
「その辺はまだよくわからないんだけどね、ヒトミ。」
ヒルデは改めて彼女、ヒトミに向き直る。
ヒトミはヒルデの近所に住む幼馴染だ。彼女はドイツ人の父と日本人の母の間に生まれた
ハーフで、東洋系の面立ちながら、アイスブルーの瞳をもつ魅力的な少女だ。
父が空手の道場を経営しており、彼女は幼い頃からその父の影響で空手に打ち込んでいる。
その腕前たるや、既に道場の練習生では誰も適わない程である。
そんな超体育会系の彼女とピアノ少女のヒルデが何故息が合うのかはよくわからなかったが、兎に角、彼女はヒルデの無二の親友であった。
ヒルデが切り出した。
「それでね、ヒトミ。その人、ドイツ語がわからないみたいなの、聞いた感じが日本語みたいでね。
英語は少しわかるみたいだったから、辛うじて意思は通じるんだけど。」
彼女が話しているのは、一昨日助けた見知らぬ男の事だった。
何とか男の下から這い出した彼女は先ず父を呼びに走った。
父は駆けつけるや、ピアノ教師の小屋へ急いだが、あいにく教室にはその男を休ませるような適当な部屋などはなく、
幸いにも怪我自体はそれほど深刻でもなかったので、仕方なく男はヒルデの自宅で助けることとなったのだ。
その日の晩、彼は意識を取り戻したのだが、どうにも言葉が通じないのだ。
辛うじて初歩的な英語は理解できるようだったので、できる範囲で事情を聞こうと思ったところ、
つい先程目覚めるまでの記憶が一切ない、と彼は言う。
初めて会った時の恐怖感はもうなかったが、記憶がないということが、ヒルデには気がかりだった。
「つまり、私に彼から日本語で色々聞いて欲しい、ってことね?」
一通りの情報を聞いたヒトミが、ヒルデの先を言う。
彼女は元々好奇心が旺盛な性質なのか、母に習って、日本語もかなり流暢に話すことができる。
何度か日本にも行っているらしく、妙に日本文化にも詳しい。
「そうなの、お願いできる?」
ヒルデが申し訳なさそうに尋ねる。
「勿論!そんなことお安い御用だわ。」

ヒトミは屈託なく笑って言った。
*
ヒルデの自宅は、彼女達の通う学校からバスに乗って10分、更にそこから歩いて5分程の所にある。
ヒトミとは自宅に荷物を置きに帰るといって、一度別れた。
「ただいま。」
いつものように玄関をくぐり、そのまま居間へ行く。ドアを開けるとソファには母親が座っており、ヒルデを認めて微笑んだ。
「おかえり、ヒルデ。」
「ただいま、お母さん。あの人どうなった?」
ヒルデは上着を脱いでソファに放る。母はそれを目でたしなめて答える。
「ああ、アインさん?今お父さんと話をしているわ。」
アイン、というのは彼女が名づけた名だ。
記憶喪失の彼には名前の記憶も当然ない。そうすると彼を呼ぶ時などに色々と不都合が生じるので一時的に彼に名前を与えよう、という話になったのだ。
ヒルデは彼の腕に取り付けられていた腕輪に『ε−01』と刻まれてあるのを発見し、それならばとドイツ語で『1』を表すアインという名をつけた。
「どう?少しは何かわかった?」
ひるでが尋ねると、母は全然、と肩をすくめた。
「何せ、お父さんも英語はからっきしですからね。」
と母はおどけてみせる。
そうね、とヒルデも笑った。
ヒトミが家に到着したのはそれから5分後の事だった。
彼女が今の母親に会釈してから、二人は二階の彼――アインがいる部屋へ向かった。
「ねえ、ヒルデ。そのアインって人、カッコいいの?」
ヒトミが茶化すように尋ねる。
「ん、うん。目鼻立ちは凄く整ってると思うよ。身体つきも何かやってそうな凄い筋肉してるし。」
ヒルデは怪訝な目を向けて答える。
「ふぅん。じゃ、うちの道場に来ないかしら、その人。」
取りとめもない話をしているうちに、彼女達は部屋の前に辿り着いた。
軽くノックをして、ヒルデは扉の向こう側に呼びかける。
「お父さん、入るよ。」
「応、いいぞ、入れ。」
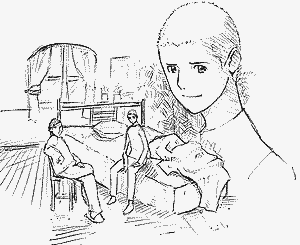
扉の向こうから低いよく通る声が聞こえてくる。
それを確認してから一呼吸置いて、ヒルデは扉を開けた。
ヒトミを伴って部屋に入ると、ずんぐりとした髭面の男――父と、
父の寝間着を借りて身に付け、ベッドに腰を預けている長身の男、アインがいた。
アインはヒルデを認めると穏やかな笑みを浮かべる。
ヒルデはその表情に思わずドキリとしてしまった。
そんな些細な変化には気にも留めず、父が切り出した。
「おお、ヒトミちゃんつれてきてくれたか。」
「はい、おじ様、お久しぶりです。」
ヒトミが恭しくお辞儀をした。
「じゃあ早速だけどヒトミちゃん、お願いできるかな。」
と、ヒルデの父が今し方自分が座っていた椅子を勧める。
ヒトミは促されるままに椅子に腰掛けると、アインに体を向けた。
ヒルデはその彼女の傍らに立つ。
ふぅ、とヒトミが軽く息をついた。幾分緊張しているのだろうか。
そして、
『はじめまして、アインさん。私はヒトミって言います。』
彼女は非常に流暢な日本語で話し始めた。
アインは初め、驚いたような表情を浮かべ、それから安心したように話し始めた。
『こちらこそ、ヒトミ。聞いていると思うが、ヒルデに名づけて貰ったので今はアインだ。よろしく。』
『よろしく、アイン。それで、こんなに話せるんだし、やっぱり貴方は日本人よね?』
取りあえず無難な所から切り出してみる。
『一番しっくり来る、話しやすい言葉は日本語だから、そうだろうな。』
どうやら彼は自分がどこの生まれかについても自信がないらしい。
『貴方は本当に記憶がないの?』
ヒトミは思わず一番聞きたいことを聞いた。
するとアインは、にわかに眼光を強め、こわばった表情を浮かべた。
『本当にどうしてあの森にいたのかはおろか、自分が何者なのかさえ全くわからないんだ。』
そういってアインは俯く。
傍で見ていたヒルデ心配そうにヒトミを覗き込む。なるべくアインには聞こえないような小さな声でヒトミに話し掛ける。
(やっぱり、駄目なの・・・?)
ヒトミが沈痛な面持ちで頷く。そして彼女は意を決した様に、アインに向き直った。
『とにかく、何かと不自由するだろうから、ドイツ語を覚えましょう。暇な時間には私も来るわ。貴方が誰なのかは、それから考えましょう?』
その言葉に、物思いに沈んでいたアインの顔が、僅かに和らいだ。
*
うだるような炎天下の住宅地におよそ似つかわしくない、元気の良い掛け声があたりに響いていた。
それは小学校の体育館ほどもある、大きな石造りの建物の中から聞こえてくる。
ここはヒトミの父親が運営している、空手の道場だった。余りにも暑い夏の陽射しのため、
今は道場の扉は全て開け放たれている。そこから覗く、練習中の道場生の中に、彼――アインはいた。
全員揃っての基本の移動稽古をやっているらしく、アインは整然と並んでいる列の一番後ろで練習にいそしんでいた。
その列の先頭には、他の道場生と同じ道着を身に付けて練習をするヒトミの姿もある。師範らしき長身白髪の男が声を張り上げる。
「次!上段流し受けから逆突き!」
その掛け声に、アインを含め、道場生が気合いを放つ。
『押忍!!』
あれから10ヶ月近くが経とうとしていた。
アインは、ヒルデの家で世話になりながらヒトミからドイツ語を習った。
英語さえ満足に話せないため最初こそ苦戦したが、アインは3ヶ月ほどで日常会話程度のドイツ語をマスターした。
その後は、アルバイトなどをして幾ばくかの金を稼ぎ、ヒルデの家に収めながら、自分を探す毎日を送っていた。
そんな中、ある時用事でヒトミの家を訪ねたアインは、一つの衝撃と出会った。
それが、空手だった。初め、道場で空手の練習を目撃した時、彼の体に何ともいえない感情が湧きあがった。
それは懐古の念のようでも有り、望郷の念のようでも有り、同時に憎しみの念のようでも有った。
その陰と陽のない交ぜになったような不思議な感覚に、アインはいつしか、自分の記憶が隠されているのではないかと考えるようになった。
アインが空手を始めて、早半年が経とうとしていた。
練習が終わって、アインはタオルを片手に表に出た。見上げる空は蒼く、高く、空色に輝いていた。
やや傾きかけた太陽の陽射しに目を細める。記憶を失う前の自分は、本当に何か運動をしていたのか、
体を動かす充実感は、計り知れないものがあった。
彼はまだこの道場で練習をはじめてから半年ほどしか経っていないので、
組手稽古(実際に自由に突き蹴りを繰り出して相手を打倒する練習)はやっていないものの、彼の飲み込みの良さは正直尋常ではなかった。
次第にドイツ語も、かなり自然に話せるようになり、日常生活にも何の支障もなかった。そして彼は思う。
(後は記憶を辿るのみ、か。)
その刹那、背後に突然言い知れない違和感を感じ、彼は咄嗟にその場を飛び退いた。
着地するや振り向いた先には、同じく練習を終え、涼みに出てきたヒトミがやや驚きの表情で立っていた。
彼女は道着の下にブルゾンと同じ鷲のエンブレムの入った、チューブトップの水着のような衣服を着用している。
それが目のやり場に困らなくもないが、彼女の場合、健康的なイメージの方が勝っている。
「驚いたわ、後ろから小突いてあげようと思ったのに。」
彼女は破顔すると、悪びれずに言う。
「すまない、ヒトミ。自分でもなんだかよくわからないんだ。」
立ち上がって応じるアインの胸中にはしかし、疑念が芽生えていた。
(今のは一体・・・。何故背後に彼女がいると気付いた・・・?)
彼が思案しているのを訝って、ヒトミが声をかける。
「アイン?表にヒルデが迎えに来ているわ。」
「あ、ああ。わかった。ありがとう。」
疑惑は晴れなかったが、彼は考えるのをやめた。
ヒルデがヒトミ家の居間で待つこと十数分。アインは身支度を終え、居間に姿を現した。
今の彼は薄手の白いプリントTシャツにジーパンという、ラフなスタイルだった。
1年弱も経ったいま、彼の髪は肩まで届くほどに伸びていた。身体つきこそがっしりとしているものの、
彼の整った眉目と相まって、彼はこの界隈では結構な人気を誇っている。
ヒトミの母と談笑していたヒルデは、アインを認めると立ち上がった。
「学校の講習が早く終わったからこっちに寄って見たの。もう終わる頃だと思って。」
彼女は優しく微笑む。
「そうか、すまない。それじゃ、帰ろうか。」
そう言って、アインは彼女の荷物を代わりに持ち、扉を促した。
アインを伴ってヒトミの家から出、自宅に向かって少し歩くと、民家の塀に寄りかかって、男が一人立っていた。
年の頃はヒルデと同じくらい、身長は170cm前後で優男然とした、見るからに軽薄そうな外見をしていた。
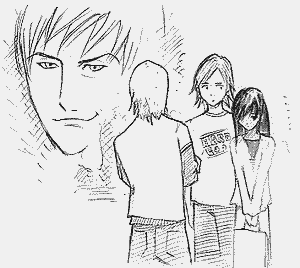
それを認めたヒルデの顔色が、にわかに曇る。
「どうした、ヒルデ。」
アインが怪訝そうに尋ねる。それにヒルデが答えるよりも早く、男がヒルデに声をかけてきた。
「やあ、ヒルデ。元気かい?」
ヒルデが一瞬身を竦ませる。どうやらこの男とは知り合いのようだ、とアインは当たりをつけた。彼は声を忍ばせて尋ねる。
「ヒルデ、知り合いか?」
「うん・・・。学校の同級生で、ニヒトくん。ローヤルコングロマリットの御曹司なの。」
ローヤルコングロマリットとはドイツに本社を置く巨大複合企業のことだ。
その資金力はちょっとした小国の国家予算ほどもあり、ドイツ国内でも、トップ企業になっている会社だった。
つまり噛み砕いて言えば、彼はとんでもない金持ちだということになる。
彼、ニヒトは薄ら笑みを浮かべた。その笑みはどこか凄惨な印象を与える、酷薄なものだった。
「そろそろ返事、聞かせてくれないかな。僕と付き合って欲しいんだ。」
彼はそう言うと、一歩彼女の方へ歩み寄った。それにつられてヒルデが一歩退く。
どうやら彼はヒルデに好意を持ち、交際を申し込んでいるようだった。
それにしてはヒルデが怯えていることが、アインには少し気がかりだった。
「ごめんなさい、やっぱり私、貴方と付き合う気にはなれないです・・・。」
ヒルデは怯えながらも、しかしはっきりと拒絶したようだ。
するとその言葉に、彼の表情が消える。
まるで機械仕掛けの自動人形のような、感情を感じさせない作り物のような顔に変貌したのだ。
「おいおい、散々待たせといて、そりゃないんじゃないの?俺はニヒト・ローエンハイムだぜ?断られる選択肢なんざ、最初からねーんだよ。」
急に汚い言葉遣いになった彼が、歩み寄ってくると、突然彼女の腕を掴んで引っ張る。
「いっ、痛い!!」
彼女は抵抗するが、女の、それもヒルデのような子の力ではとても男には適わず、次第にヒルデの体は引きずられ始める。
しかし。
「止めないか。」
ヒルデを引くニヒトの腕をアインが掴んで静止した。
「アイン・・・。」
ヒルデは安堵したように彼の名を呟く。
一方のニヒトはアインを睨み付けると、食って掛かった。
「あ?手前何だよ、手前には関係ね―だろ?」
「彼女は嫌がっている。お前は彼女に対して一方的に気持ちをぶつけているだけだ。」
対するアインはあくまで冷静に、まるで波一つない湖面のような静けさで答えた。
「っせーな。お前痛い目見たいのか・・・、な!!」
その時、尚も食って掛かろうとしていたニヒトが、驚愕の声を上げた。
アインが、掴んだ彼の腕ごと彼を持ち上げて宙吊りにしていたのだ。
幾ら中背と言ってもそれなりの体重がある大の男を、しかも片手で軽々と持ち上げたのだ。
ニヒトの驚きも至極当然のものであろう。アインはおもむろにニヒトに顔を近づけると底冷えするような声で言い放った。
「彼女は今は俺の家族のようなものだ。もしこれ以上彼女が嫌がるようなことをお前がするのなら、俺は容赦しないぞ。」
そう言うとアインは、彼を下ろし、開放した。
「わかったら、行け。」
そうアインが睨み付けると、
「ひっ、ひいいぃ!!」
ニヒトは恐怖に悲鳴を上げ、つまづきそうになりながら走り去っていった。
「・・・やれやれ。」
アインは手を払うとため息をつき、ヒルデを向いた。
「大丈夫か?ヒルデ。」
彼が声をかけると、今まで呆けていたヒルデが体の緊張をほぐし、ため息をついた。
「ありがとう、アイン。」
彼女は恥ずかしそうに俯き、それから顔を上げて言った。
「さっきは嬉しかったよ。家族だ、って言ってくれて。」
*
翌日、ヒルデは買い物があるらしく、街に出ると言った。
昨日の事を懸念していたアインは、彼女の荷物持ちとして同行することにした。
二人はバスを使って都市部へ出た。市内はそこそこ賑わっており、地方都市としてはかなり大きい部類に入る街並みだった。
新しいピアノの楽譜を買うために、二人は楽器店のある通りを歩いていた。
とある電気店の前をとおりが買った時、店先に陳列してあるテレビが、大きな効果音を放った。
「な、何?」
その音に驚いたヒルデが、足を止める。
テレビでは有名な世界格闘技大会の参加者募集を告知するCMが放送されている。
「これは?」
ヒルデの横でテレビを眺めていたアインが尋ねる。
「なんでもDead or Aliveとかいう格闘大会の二回大会の参加募集らしいわ。
結構有名な大会で参加条件を飲むなら誰でも出場できるのが特徴だったと思う。
大会予選が始まるのは確か半年後だったと思うけど。」
ヒルデも別にこういったものに興味があるわけではないので、なにかの雑誌で読んだうろ覚えの知識を喋った。
「そうなのか、Dead or Aliveね・・・。」
そうアインが呟いた時、画面に大会名のテロップが流れた。
そのDOAの文字を見た瞬間、突然彼の脳裏に何かが閃いた。
「くっ・・・。」
彼は苦悶の声を上げるとその場に膝を着いた。突然こめかみを締め付けられるような痛みに襲われる。
「あ、アイン、大丈夫!?」
その余りに深刻な症状にヒルデが駆け寄る。
彼の脳裏に閃いた映像は巨大な光だった。
いくつもの照明が自分を照らしているようだ。
視界の隅に、白衣を身に纏ったいかにも研究者然とした者たちが十数人、せわしなく動き回っている。
今度は何者かの声が聞こえてきた。
『これより、DOATECによるε計画を発動する。被験者は彼だ。』
その声を皮切りに何人もの白衣が自分を覗き込んでくる。
手に手に妖しげな注射器や道具を持って。
彼の頭痛は一分ほども続き、それから徐々に和らいでいった。
荒くなった呼吸を整えると、アインはヒルデの手を借りて立ち上がった。
「も、もう、大丈夫だ。」
そう言って心配するヒルデを落ち着かせて、アインは思案した。
(今のは一体・・・。このDOAと言う大会に、自分の何かが隠されているんじゃ・・・。)
しかし、そう考えれば考えるほど、不安とも恐怖ともつかない得体の知れない感情が湧きあがってきて、心に霞がかかったように意識が朧げになっていく。
(・・・考えるのはよそう。)
彼は無意識の内に、そう合点した。
*
買い物など、全て済ませた帰り道。日はすっかり傾き、二人の影を長くしている。
「今日は本当にありがとうね、アイン。」
ヒルデがアインを向いて言う。
「なんてことはない、当然の事だ。俺は居候だからな。」
アインが口の端を少し持ち上げて答える。
「もう、アインったら。」
その冗談につられてヒルデも微笑む。
談笑しながら二人でバス停への道を歩いていると、いつの間にやら二人は人通りの極端に少ない路地に入り込んでいた。
「なんだか、寂しい通りね・・・。」
ヒルデが不安そうに呟く。確かにその通りは表通りから見ると雲泥の差であった。
表通りにあった明るい街並みはなく、まるで世界全体が灰色になったかのような光景だ。
アインもその不自然な人気のなさを訝っていた。
(不穏な空気が流れている・・・。)
その感覚には根拠はなかった。しかし、恐らくこれも失われた記憶に答えがあるのだろう。
そんなことを考えながら足早に路地を急いでいると、行く先に見覚えのある男が立っていることに気付いた。
二人はその男を認めると立ち止まり、こわばった表情を浮かべる。
「・・・ニヒトくん・・・。」
呟くヒルデの視線の先には、昨日ヒルデに言い寄っていた、ニヒト・ローエンハイムがいた。アインは素早くヒルデの前に進み出、彼女を庇う。
「お前は昨日の・・・。」
そういうアインに、ニヒトは不敵な笑みを浮かべた。
「昨日はどうも。けどね、あんなことでは僕は引き下がらないよ。」
言い終わるや昨日と同じ、能面のような表情に変わる。
そして彼は叫んだ。
「僕はヒルデのことを愛しているんだ!彼女は僕のものだ、お前は邪魔なんだよ!」
やや狂気じみたニヒトの台詞に、ヒルデは寒気を覚える。
アインはそんなヒルデに気を配りながら応える。
「それは彼女が決めることだ。そして答えは昨日出たはずだ。」
しかし、そんなことなどまったく意にも介していないようだ。
「そんなことは関係ないよ。彼女は絶対に手に入れる。・・・、僕を誰だと思ってるんだ?」
そう言うと彼は手を掲げる。
するとどこから沸いて出たのか、周囲をニヒトを含め、八人の男が取り囲んでいた。
「これは・・・?」
アインの声音がまた低く底冷えするようなものに変わった。
油断なく彼らを観察する。いずれも手に手に鉄パイプやバタフライナイフと言った、非常にわかりやすい凶器を持っている。
ヒルデもそれを認めたらしく、悲鳴に近い声を上げた。
「ニヒト君!アインさんに何をするつもり!?」
すると彼は再び薄い笑みを浮かべた。
「僕の父の力を持ってすればね、東洋人が一人殺されたことぐらい、隠蔽出来るのさ。」
ヒルデは愕然とした。まさか同級生にこれほどまでに壊れた人間がいたとは思ってもいなかった。
「ヒルデは僕が貰う、そしてアイン君、君には死んでもらう。」
その言葉に応じて、八人が身構える。
アインは着ていた上着を油断なく脱ぐと、それをヒルデに渡した。
「ヒルデ、悪いが少し離れていてくれ。」
そう言って彼女を押し、彼から離した。ヒルデは何か言いたそうだったが、結局押し黙り、不安そうな表情で彼を見つめている。
アインはゆっくりと基立ち(空手の基本的な立ち方で両腕を胸の高さで構え、足を肩幅に開いて立つ立ち方)で左半身に構えた。
「悪いがこちらも命がかかっているんでな、手加減は出来ないぞ。」
そう宣言する彼が、ヒルデにはどこか嬉しそうに見えた。
最初に仕掛けてきたのは顔中に痛々しいほどのピアスを施した男だった。
握り締めた鉄パイプを最上段から振り下ろす。アインは冷静に半歩進んでポイントをずらし、
上段受けで鉄パイプを受けると、返す拳で顔面に逆突き――アインの道場では吾妻という――を繰り出す。
突きは狙いたがわず鼻っ柱に命中。その一撃で男は数m吹き飛んだ。
その背後から今度はバタフライナイフを腰だめに構えた髪を緑色にブリーチした男が走ってくる。
男がナイフを突き出すより疾く、振り返ったアインの上段後ろ廻し蹴りが男の側頭部に炸裂する。
足を引いているところに三人目の男が素手で殴りかかってくる。体勢が崩れているところを見てかかってきたのだろう。
アインは引き足を振り回してバランスを取り、そのままその足で男の喉仏に足刀蹴りをお見舞いする。
やや怯えたような金髪の男が奇声を上げながらチェーンを振り回して走ってきた。
アインはチェーンを避けるように深く体を沈み込ませ、そのまま縮んだ体を全力で伸ばすと相手の顔面と鳩尾に双手突きを繰り出す。
喰らった男は前歯を全て失い、鳩尾への一撃で意識を手放した。
最後に襲い掛かろうとしていた小太りの男は余りの惨状に立ちすくんでしまった。
アインはその男に向かって走り、跳び上がると空中で半回転し、そのまま踵で相手の顎を蹴り割った。(風雲という)
着地したアインが息吹(空手の呼吸法)で呼吸を整えて構えなおした周りには、
死屍累々(実際には気絶しているだけだが)と男達が倒れ伏していた。
あっという間の出来事に、残った連中は3人だった。皆一様に信じられないといった表情でアインを見つめている。
それはヒルデも同じ気持ちだった。果たして空手を始めてたかだか半年の男が、ここまで戦えるものなのだろうか。
(やっぱりきっとアインは元から何かやってたんだわ・・・。)
そう考えるヒルデの思考は至極当然だった。
当の本人が、一番驚いていた。
確かに師範やヒトミには覚えがいいと言われていたが、まさか実際に一体多数で殴り合えるほどに戦えるとは思ってもいなかったのだ。
そしてそれ以上に。
(なんだ、この湧き上がる感覚は・・・。)
戦いの最中から、アインの体はとある感情に震えていた。すなわちそれは、歓喜だった。
それは決して、アインの心が戦いを求めていると言うことではない。むしろ戦いを求めているのは、彼の体だった。
(俺は一体、何者なんだ・・・。)
一番最初に正気に戻ったのはニヒトだった。
震える足を何とか奮い立たせ、彼は不敵に笑った。
「まさか、本当に一瞬で五人を倒してしまうとは思いもしなかったよ。」
その声に構えを解いたアインの一層厳しくなった視線が刺さる。
彼の両拳は血に塗れていた。幾ら自衛のためとは言え、まともな神経をしていれば、人を殴って何とも思わずにはいられないのだ。
「もう三人がかりでも無理だと言うことはわかったろう。わかったら大人しく引いてくれないか。」
アインがつとめて冷静に言う。
ニヒトは他の二人と小声で何か話すと、三人揃って懐に手を伸ばした。
再び出てきたその手に握られていたものを見て、今度こそアインとヒルデは凍りついた。
それは拳銃だった。
詳しくはピエトロベレッタ社製のベレッタF93Rと言う銃だ。
軍隊などで使用されている3バーストも可能な、一般人が持つような銃ではない。
ニヒトが再び凄惨な笑みを浮かべ、銃口をアインに向ける。同時に他の二人も銃口を向けた。
「あ、アイン!!」
ヒルデが悲鳴を上げる。目の前で今まさに殺人が起ころうとしているのだ。まともな女子高校生には耐えられないのも無理はない。
三人がスライドを引き、ハンマーを下ろす。
身構えたアインの頭の中は真っ白だった。
(こ、殺される・・・。)
その時、再び脳裏に映像がよぎった。
それは少女だった。色素の薄い栗色の髪を三つ編みにした、意志の強そうな瞳の可愛らしい少女がこちらを振り返って微笑んだ。
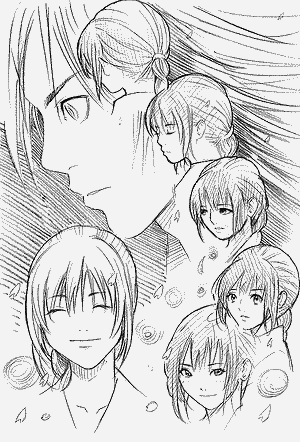
――俺は・・・死ねない!!
だんっ、だんっ、だんっ
いやあああぁぁぁぁぁ!!
ヒルデの悲鳴と三発の銃声が路地裏にこだました。
そこにあるべき彼の死体は存在しなかった。ニヒトら三人は全く目を瞑ってはいなかった。なのに彼はその場から消えたのだ。
がしっ
「ひぃっ!!」
突然後ろから誰かに首をつかまれて、ニヒトは声を上げた。
首を掴んだのは鬼の形相で彼らを睨みつけるアインだった。

アインは無言で彼らを睥睨する。その眼光は、それだけで彼らを殺してしまうのではないかと思われるほどに、鋭かった。
「うわ、うわああぁぁぁぁぁ!!」
余りの恐怖に錯乱した一人が、アインに銃口を向ける。
それよりも早く、アインはニヒトを彼に向かって投げつける。
それに一瞬怯んだ彼はニヒトに潰される形で倒れた。
アインはそのままもう一人の男の懐に飛び込むと銃を手刀で叩き落し、鳩尾に膝蹴りを喰らわせる。男はその場で気絶した。
ニヒトが、下敷きになって気絶した男に構わず立ち上がって、再び銃を構える。
またもアインの姿が掻き消え、目の前に現れる。ニヒトは声を上げる間もなく銃を叩き落され、
首を掴んで持ち上げられる。アインは更にその手に力を加える。
「もし今度、ヒルデの前に現れてみろ。その時はお前を殺す。」
呟くような単純な言葉だったが、その声は呪詛のようにニヒトの心に染み込んだ。
「あっあっ・・・。」
ニヒトは意味不明な声を上げ、必死に頷く。
アインの突きが彼の鳩尾に炸裂したのは、直後だった。
*
その後の事をアインはなんだかよく覚えていなかった。
ヒルデの父親が彼らを迎えにきたことは覚えている。
ヒルデが震えながらも何かを話し掛けてきたのも、覚えている。内容までは覚えていなかったが。
自宅に帰り着いたアインは、その後3日、眠りつづけた。
原因は何なのか判っていなかった。
そして3日後の朝、目を覚ましたアインはヒルデの部屋を訪ねた。
ヒルデが気遣うような視線でこちらを見ている。
彼女は、自分がとんでもない悪魔かもしれないとわかった今でも自分のことを気にかけてくれているのだ。
そのことがアインを少しだけ救った。
少しの間気まずい空気が流れたが、アインは意を決して口を開いた。
「俺、Dead or Aliveに出てみようと思う。」
「えっ?」
その言葉は余りにも唐突で、ヒルデは思わず声を上げてしまった。
当惑するヒルデを制してアインが続ける。
「今朝目が覚めてから考えていたんだ。あのDOAの文字を見たとき、頭の中になにかの映像が浮かんだ。
戦っている時も。この二つから考えても、どうやら俺は戦うことで生きていた人間らしい。
謎を解く鍵はきっとあの大会にある。だから、俺は行くよ。」
穏やかな目でそう締めくくると、アインはヒルデを見た。
ヒルデは神妙な面持ちで何か思案していた。
そして顔を上げたヒルデは、目尻に涙を浮かべていた。
「わかったよ、アイン。けど約束して。記憶を取り戻そうが戻すまいが、必ずもう一度会いにきて。」
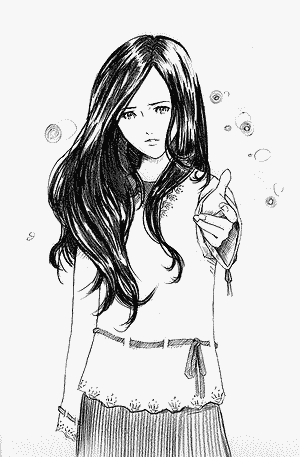
そう言ってヒルデは右手を差し出す。
「ああ、約束する。必ずもう一度、君に会いに来る。」
決意の瞳をヒルデに向け、アインはその手を取った。
*
――そして、彼はこの家を去りました。
彼はまだ私のところに会いにきてはいません。
*
ヒルデの元に、日本から一通のエアメールが届いたのは、Dead or Aliveが終了してから2週間後のことだった。
FIN