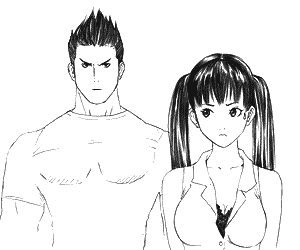
男――ジャン・リーも、闘いのときに見せる、それだけで睨み付けた相手を殺してしまいそうなほどの鋭い視線はなりを潜め、
しかし、眉間にしわを寄せた表情のまま、答えた。
レイファンとジャン、この二人には浅はかならぬ因縁があるのだが、お互いにDead or Arive以外で会うことはほとんどなかった。
それが偶然にもこの日、二人は出会ってしまったのだ。
それはDead or Arive二回大会が終わって半年程たったある日曜日のことだった。
季節は冬であったが、今日は久しぶりの小春日和で、休日であることも幸いし、通りは買い物客や何やらで人通りが絶えなかった。
そんなうららかな日差しが心地よい昼下がり、有名な快餐店(いわゆるファーストフード)の前に、
互いに微妙にぎこちない表情を浮かべた二人の男女がいた。
「なんていうか・・・、奇遇ね。」
女――レイファンはようやくそれだけを口にした。
「・・・だな。」
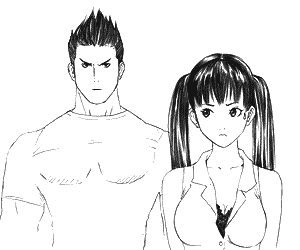
男――ジャン・リーも、闘いのときに見せる、それだけで睨み付けた相手を殺してしまいそうなほどの鋭い視線はなりを潜め、
しかし、眉間にしわを寄せた表情のまま、答えた。
レイファンとジャン、この二人には浅はかならぬ因縁があるのだが、お互いにDead or Arive以外で会うことはほとんどなかった。
それが偶然にもこの日、二人は出会ってしまったのだ。
「とりあえず、入らない?」
立ち話も何だと思ったので、彼女はそう提案する。
「・・・そうだな。」
彼も仏頂面で言葉少なに答えた。
窓際の席に座った二人は最初数分、互いに自身の注文した品をつつきつつも、沈黙を守ったままであった。
Dead or Aliveのときでこそ、死力を尽くして闘い、言葉は少ないながらもその拳で多くを語り合った二人だったが、
実際に闘いの場以外で会うと、ある意味当然かもしれなかったが会話が見つからなかった。
レイファンは烏龍茶をすすりつつ、ジャンを盗み見る。
彼は何を考えているのか、相変わらずの仏頂面で三文治(サンドイッチ)を口に運びながら窓の外を眺めていたが、
ふと視線をこちらに泳がせた。
当然の如く二人の視線が交錯し、すぐにまたお互い目をそらす。
(な、なんか、勢いで誘っては見たものの、気まずいわ・・・。)
彼女は既に若干後悔し始めていたが、このままでは埒があかないと、思い切って切り出した。
「貴方は?今日は何しに来たの?」
「ん?ああ、新しいテーピングを買いにな・・・。」
「ふぅん・・・。」
・・・会話終了。
(しまったわ、もっと会話を広げるんだった、何納得しちゃってんのよ、私!)
心の中で猛省してから、改めて話題を探す。
しかし、よくよく考えてみたが、彼女とジャンには共通の話題といえるものは、ひとつを除いて、他に存在しない。
そのことに今更ながら気づいて、彼女は内心ため息をつく。
(そうよね、よく考えたら、DOA以外でジャンとあった事ってほどんどないし。)
目の前にいる彼の厳しい眼差しを見て、彼女は初めて彼と出会った時の事を思い出した。
「貴方って。」
突然言ったレイファンの言葉に、少し遅れてジャンが応じる。
「何だ?」
「貴方って、初めて会ったときもそんな厳しい目つきをしてたわ。」
*
きっかけはほんの些細な出来事だったと、レイファンは思っている。
あまりにもしつこく声を掛けてくる大学の同級生が、ついに我慢の限界を迎えて彼女に言い寄ってきた。
多少荒っぽい手段だったのだが、生来負けん気が強い性格も災いして、彼女はその同級生を天下の往来でのしてしまったのだ。
これに懲りて普通は引き下がるところだが、そこは流石にあきらめの悪い男らしく、その男は、友人であろうか、
仲間を十数人も集め、今度はさらに手荒な方法で彼女を襲ったのだ。
フェンスと土塀に囲まれた小学校の体育館程もあろうかという空き地で、彼女は追い詰められていた。
もう習い始めて数年ほども経つ太極拳は、通っている武館では天才とさえ囁かれるほどの腕前であったが、
一対多数の乱戦の経験など皆無であり、彼女も胆を冷やしていた。
同級生の男が下卑た笑いを浮かべる。
「ようレイファン、この前は随分恥かかしてくれたじゃねーか。」
男の余りにもテンプレートな台詞に、彼女は内心ため息をついた。
しかしながらもうそれ程余裕はなく、十人を超える男たちはじりじりと間合いをつめ、今にも飛び掛ってきそうな勢いだ。
(さすがに、ちとやばいかしら・・・。)
彼女のこめかみに嫌な汗が伝い始めたその時だった。
「随分と古風な真似だな・・・。」
突然辺りによく通る低音の声が響いた。本当に何の前触れもなく聞こえたその声に、その場にいた全員が振り返った。
そこには、年の頃は二十歳前後だろうか、短く刈り込んだ髪を逆立て、
見るものを凍りつかせるような白刃の如き眼光を持つ男が立っていた。
男は、服の上からでもはっきりと分かるほど鍛え上げられた肉体を持っており、
見るからに険悪な風体の男たちにまったく物怖じもせず、
悠然とその場にいる者達を睥睨している。
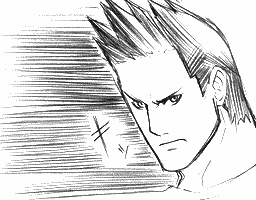
「あんだ?てめーは。ラリってスーパーマンにでもなったつもりか?」
男のまたしてもテンプレート過ぎる台詞に取り巻きの男たちも声を上げて笑う。
現れた男は静かに瞑目すると、
「義を見てせざるは勇無きなり、と言うしな。」
手首を捻ってストレッチさせながら小さな声で言った。
そして再び開眼すると、男は僅かにその場で跳ね、リラックスして極端な半身に構えた。
「お前らの様な分かりやすい連中には、言葉は要らないだろう。かかってきな。」
その一言でその場の空気が一瞬にして固体化したかのように、重苦しくなった。
言われた男たちはおろか、助け舟を出されたはずのレイファンでさえ、微動だにできない、そんな空気だった。
重苦しい沈黙を破ったのは、やはり同級生の男だった。
「い・・・、言ってくれるじゃねーか、この野郎。皆、やっちまえ!!」
その一声で、男たちは標的を目の前の男に切り替え、思い思いの武器を手に、男に躍りかかった。
それから先のことは、まったく持って圧倒的の一語に尽きる。
男の半身から繰り出される裏拳が、一直線に飛びかかってきた男のこめかみにめり込んで、殴られた男が吹き飛ぶ。
横合いから振り下ろされた鉄パイプを、鉄でできていることを物ともせずに外側へ受けて流し、返す正拳を鳩尾に叩き込む。
バタフライナイフを手に突進してくる男の刺突を向かい合った手で脇にそらし、顔面に鉄槌打ちを見舞う。
男の戦いぶりは、全ての攻撃がその制空権に入るや否や、いなされ、外され、受けられ、返す拳が相手の急所に吸い込まれる様に命中する、
という全ての動作が一拍子で行われる理想的な攻撃だった。
レイファンが自分を人質に取ろうと向かってくる男の即頭部を旋風脚で蹴り倒したときには、戦闘はあらかた片付いていた。
その場で動いている者は、既にレイファンと男以外には存在しなかった。
「大丈夫か?」
男がレイファンに近寄ってきて、話しかける。
「ええ、助かったわ。ありがと。」
彼女は辛うじてそれだけを口にしたが、その胸中を悟られまいと必死だった。
はっきり言って、それは憧れだった。
自分は特に理由があったわけではなく始めた太極拳だったが、今では自分の体をより上手に動かすこと、
またそれによって人よりも強くなれることに、確かなやりがいを感じていた。
彼の動きは、まさに彼女の目指さんとする強さをそのまま体現していると思えた。
それほどに、彼の動きは洗練され、まるで舞踏でも舞っているかのような動きだった。
色々な感情が交錯し、いまいち形にならず、俯いて沈黙していたレイファンだったが、
彼がその場を去ろうと振り返ったのを見て思わず叫んだ。
「あ、貴方の名前は!?」
男はゆっくりと振り返ると、口の端を僅かに持ち上げた。
「ジャンだ。ジャン・リー。」
そう言うと彼はまた振り返り、背中越しに右手を挙げながらその場を立ち去った。
彼女に鮮烈な衝撃を残して。
「そうだったか・・・。」
当時のことを思い出すように瞑目したジャンが、しみじみと言った。
「うん。貴方の視線、助けられた筈の私がびびっちゃうくらいだもの。」
レイファンはからからと笑った。
「その時かしらね、貴方に挑むようになったのは。」
「変なストーカーがくっついてくるようになったな。」
ジャンがからかう様に言った。
レイファンも間髪いれずに弄んでいた丸めたストローの空袋を投げつける。
(なんとか、間が持ってるわ・・・。)
彼女は半ば感動さえ覚えながらそう思った。
やっぱりどうやらこの男、闘う事に関する話にしか食いついてこないようだ。
ある程度予想こそしていたものの、実際にそうであると分かると、やはり少しこの男が変人に見えてくる。
(ともあれ、この調子で話題を振っていけばいいわけね。)
そう合点すると、レイファンは切り出した。
「もう貴方の所にも来た?招待状。」
「ああ、もうエントリーも済ませてある。」
招待状、と言うのは勿論第三回Dead or
Aliveの参加告知兼招待状だ。
ジャンが顔の向きは変えず、目だけを彼女の方に向ける。
「お前、また出るのか?」
その問いに、一瞬キョトンとなるレイファンだったが、
「勿論、貴方が出るんだから。出るに決まってるでしょ?」
直ぐにニヤリと笑うと宣言した。
「二回大会が終わってからだって、ずっと練習してたんだから。」
そう言って、ジャンを見据える。
「今度こそ、貴方に勝つために、ね。」
そう。この男に勝つために、今の私は鍛えてるんだから。
*
「ほっほ、なかなかやるの・・・。」
その声がレイファンの耳に入ったのは、ちょうど日課の套路(中国拳法で言う型)を一通り打ち終えた時だった。
時刻はまだ早朝。澄んだ空気を呼吸しながらの修練は気持ちが良いと、彼女はいつもこの時間を選んでいた。
昔の拳法家は、他人に功夫を盗まれることを恐れたり、文化大革命の時代には弾圧されたりすることを恐れ、
夜間や日もあけない内に人に見られないように修練を積んだそうだが、この情報化の時代に秘密の修練も何もないと、
レイファンはいつも自宅アパートの裏手にある空き地で修練を行っている。
だから、人に見られることは結構あったし、それを気にしたこともなかったのだが、大抵は直ぐに気配に気づくことができていた。
しかし彼女は、この声の主がこの場にいることに、声をかけられるまで気づかなかったのだ。
(この私が、全く気配に気づかなかったなんて・・・。)
レイファンは驚愕の眼差しでその人物を観察した。
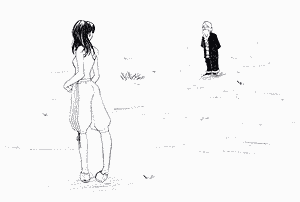
年の頃は7,80歳程だろうか、
白くなった数少ない髪の毛が寂しそうに生えているのとは対照的に豊かに蓄えられた白髭が目を引く、
人のよさそうな人相の老人だった。
小柄なその老人はレイファンよりも背が低く、手足もまるで枯れ木のようだ。
しかし、レイファンにはわかったのだ。この老人には何かとてつもない力が秘められている、と。
老人がいつまでもニコニコと笑顔を浮かべたまま体の後ろで腕組みしたまま佇んでいるので、
レイファンはついに痺れを切らして話しかけた。
「おじいさんも、太極拳やるの?」
彼女の背後をとった事からも、この老人が何がしかの術を会得していることは間違いなかった。
「ふぉふぉ、ま、少しぢゃがの・・・。」
老人はその髭をなにやら触りながら、嬉しそうに答えた。
(なにが『少し』よ。好々爺然としていながら中々の爺さんじゃない。)
そう一人思ったレイファンだったが、おくびにも出さず、
「どう?私の太極拳。自慢じゃないけど、結構得意なの。」
しっかり値踏みをし始めた。
一体この老人はどれ程の功夫を持っているのだろう。次第に彼女の胸中はざわめき始めた。
老人は、そんな彼女の心境を知ってか知らずか嬉しそうに目を細め、言った。
「何、確かに年の割には良くやるようじゃがの、お主悩んでおるな。」
「・・・。」
レイファンは二の句が次げなくなった。
どうやらこの爺さん、本当に只者ではないようだ。
そうなのだ。
彼女は、去るDead or
Aliveで自身の目標とするジャン・リーに二度挑み、二度とも辛酸を嘗めさせられているのだ。
一度目の敗北から、自分なりに本気で修練に打ち込み、功夫も積んだはずであった。
しかし結果は変わらず、二回大会でも力及ばなかったのだ。
「どうして、そんなことが言えるの・・・?」
彼女は修練を終えた後で額に浮かんだままの汗を拭うことも忘れ、尋ねた。
「ふぉふぉ、お主の拳を見れば一目瞭然じゃ。優れた套路は己を映す鏡ともなる。お主が心迷えば拳は曇り、勁は体を通らん。」
老人はなおも面白そうに笑んだ。
「お主には化が足らんの。確かに余程の天秤を持って生まれたようじゃ、その歳でそこまで太極拳を使いこなせる者はそうおらんじゃろう。
しかし化勁とはただ相手の攻撃を受け流せばよいと言うものでもない。四両撥千斤という言葉を聞いた事があるじゃろう。
真の化勁とはこちらはただ手を動かすのみで相手を倒すものじゃ。それを会得せずに実戦で太極拳を用いるのは少々危ないのう。」
老人がそう締めくくった時には、レイファンは完全に老人の言葉に聞き入っていた。
この老人の言っていることは全てあっているのだ。ここに来て彼女は太極拳の奥深さに壁を感じ始めていたのだ。
それからどれくらい経っただろうか。
日は昇りきってはいないものの、既に辺りには人の気配がし始めている。
神妙な面持ちで考え込んでいたレイファンは、意を決して顔を上げ、老人を見た。
「おじいさん。」
「んむ、なんじゃ?」
いつの間にか老人の顔からは笑顔が消えている。
「私に・・・。」
レイファンはそこで一度言葉を切った。拳を握って息を吸い込む。
「私に太極拳を教えてください。」
きっとこの老人は私を今よりももっと強くしてくれる。
会ってからたかだか一時間程度だが、彼女には直観があった。
老人はまたも、面白そうに髭をさすった。
「ええよ。」
「・・・。」
(そ、即答って・・・。)
普通こういう場合、『わしは弟子を取らん主義での。』とか言いそうなものである。
他人に自分が学んできたものを授けるのだから、それくらいは当然のことなのだ。
(それをこの爺さんは・・・。)
全くこの老人の心理が読めない。
「あの、そんな簡単に言っちゃっていいの・・・?」
レイファンが恐る恐る聞くと、
「何、そんなに勿体ぶる物でもないしの。それに・・・。」
言って老人は歯を剥いて見せた。
「最初にお主を見た時から一目惚れしてしもうての。」
この老人、名前を李というらしい。
太極拳の達人なのだから、ついつい太極拳発祥の地であり村人が全員親戚であることでも有名な
陳家溝の陳氏を想像してしまう(とんでもない偏見だが)のだが、どうやらこの老人はその家系ではないようだ。
李老師とは、レイファンが練習を始める時間に空き地で落ち合い、そのまま日の出まで修行をするという形をとった。
レイファンには大学生と言う本文がある。はじめ、彼女は李老に大学を休学する覚悟も出来ていると言ったが、李老はそれを許さなかった。
「武術とは善く生きる為の術じゃ。故に自分の人生を歩んでゆく手段といってもいい。
その武術を学ぶために今の生活を変えるのは本末転倒じゃ。」
というのが、老師の言である。
本来ならば勉強の時間も惜しいくらいなのだが、そこは李老に弟子入りしたてまえ、
師匠の教育方針に口を出すのはお門違いである。
こうして、レイファンと李老人の太極拳修行生活が始まった。
はじめ、李老は彼女に最も基本的な三動作だけを徹底的にやらせた。
日が昇るまでの2時間程の時間を全て、である。
(毎度のことだけど、もう体に力が入らないわ・・・。)
練習が終わるころには、彼女はいつもへとへとになっていた。
李老は楽しそうに髭をさする。
「お主は女性じゃから、基本的にはその動きは柔らかい。
しかし本質的にはやはり人間じゃ、体のいたるところに余計な力が入っておる。まずはそれを抜くことから始めようかの。」
聞けば理屈は納得できるのだが、どうにも修行の実感が沸かない。
「ホントに毎日こればかりやり続けるの?」
レイファンはいささかうんざりした様子で尋ねた。
「奥義というのは基本の中に内包されておるものじゃ。お主は既に一通りの套路を覚えておるじゃろ?
じゃから、基本の真髄を体感するだけでも十分に伸びるわい。じゃが、いつまでもそれだけの言うのも、つまらんじゃろ?」
李老が悪戯っぽく言う。
「そう思って、お主にはもうひとつ、伝授しようと思っておるものがある。」
李老はそう言うと、その場で起勢式(始めの姿勢)をとった。
そして、李老が打った套路に、レイファンは驚愕した。
李老の動きはおよそ太極拳とは思えない剛猛な発勁を連発するものだった。
しかしだからといって、彼の動きは全く固くはない。むしろ、その途切れない流れは太極拳そのものだった。
まるで、長江を流れる川が静かな清流から荒々しい激流が起こす大波に変貌するかのようなものだった。
李老が套路を終えて、呆けたままの彼女に向き直った。
「これは忽雷架といっての、まるで雷が落ちるように発勁を連発することから名づけられた套路じゃ。
お主が基本の極意を体感できれば、この忽雷架も体得できよう。だが、忘れてはいけないのは捨己従人じゃ。
己を捨て、相手の動きにあわせることで、四両の力で千斤の攻撃を跳ね返す。これこそが太極拳の真骨頂じゃ。」
老人が満足そうに髭を触った。
レイファンは開いた口が驚きの余りふさがらなかった。
偶然出会った、一見今にも倒れかねない老人が、まさか自分にこれほどのものを授けてくれるとは。全く以って幸運である。
しかしこれさえマスターできれば、また彼に挑める。今度こそ、彼に勝つことが出来るかもしれない。
(待ってなさい、ジャン!)
呆けていたレイファンは、気を取り直して拳を強く握ると再び基本の動作を打ち出した。
*
所戻って快餐店。
向かい合うレイファンとジャンの間には再び沈黙の帳が下りつつあった。
レイファンは今日何度目かも分からない後悔をしていた。
(せっかくいい感じで会話できてたのに、まさか私が物思いに耽って会話が終わるとは・・・。)
今度は自分のせいだったので、目の前で窓の外を眺めるジャンのせいにすることもできない。
(ホント、どうしようかしら。この状況。)
などと、彼女がそろそろ解散を切り出そうかと思案し始めたその時だった。
「おいねーちゃん!こりゃどーゆーこった!!」
なんだか胸が悪くなりそうな怒号が、自分たちの席から三つほど離れたボックス席から聞こえて、
レイファンとジャンは同時に目をやった。
そこでは4,5人の柄の悪い男たちが気の弱そうな女性店員に何事か文句をつけて怒鳴り散らしていた。
「な?ねーちゃん、分かる?俺のコーラにゴキブリがはいってたわけよ。」
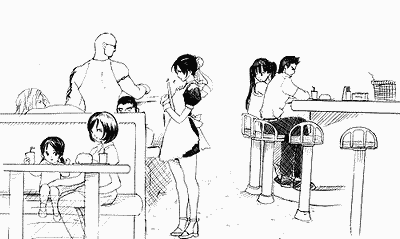
彼らのリーダー格らしき男がしきりに喚いているその内容を聞いて、レイファンは思わずため息を漏らした。
「最近分かりやすい奴らって流行ってるのかしらね。」
彼女のため息に賛同するように、ジャンも嘆息した。
「全くだ。まあ、ここで見たのも何かの縁だ。助けてやるか。」
「そうね。『義を見てせざるは勇無きなり。』だったっけ?」
レイファンがからかい半分で言うと、ジャンは少々気分を害したらしく、
露骨に不満そうな目でこちらを睨んでいた。
その視線に肩をすくめながら彼女は微笑し、二人は立ち上がった。
テーブルに歩み寄って女性店員の前に進み出る。
「どうやったらカップの中にゴキブリが入るんだ?俺にも教えてくれよ。」
ジャンが幾分挑発的な口調で問う。
言われた男たちも条件反射のように睨みつけて来る。
「あ?お前らにゃ関係ねーよ。失せな。」
ジャンとレイファンはいったんお互いに顔を見合わせ、ため息をつく。
「お前らのせいで飯がまずくなってんだよ。」
「あ?お前らおもしれーな。遊んでやっから表出な。」
リーダーらしき男が言った台詞は、この二人が何者か知っている人間が聞けば、お前が言うな、と思ったかもしれない。
快餐店の裏路地で、向かい合うようにして、レイファンたちと男たちは対峙していた。
「分かってると思うが、もう謝ったって許してやんねーぞ?」
そういうと、男たちは手に手に凶器を持った。
ナイフや鉄パイプ、チェーンなど、中々に古典的な凶器を手ににじり寄ってくる男たちに、レイファンもジャンも正直呆れていた。
(ま、たいした相手じゃないでしょ・・・。)
(だろうな。凶器の握り方が、見た目に素人だとわかるしな。)
幾多の修羅場を潜り抜けてきた二人の若者は至って冷静だった。
「やっちまえ!!」
リーダーの男の掛け声とともに、男たちは顔を見合わせてうなずいてから、全員でレイファンに殺到した。
通常喧嘩などでは、真っ先に強い方を倒せばいい、という考え方をよく聞くであろう。
この場合、女のレイファンより、見るからに化け物じみたジャンの方に攻撃を仕掛けるのが得策と考えるかもしれない。
しかしそれは、半分正しいが、半分間違っているといえる。
強い方に先に攻撃を仕掛けて、戦闘が長引いた場合、かえってこちらにも損害をだし、残る相手を倒せなくなる場合があるからだ。
しかもこの場合、レイファンは女だ。彼女を倒せば、それによって、ジャンが冷静さを欠くことも考えられる。
そうなれば、頭に血が上った男など、4,5人仲間がいればどうということはない。
男たちはそう考えたのだろう。
そういう意味で、この男たちは多少場数を踏んでいるのかもしれない。
「おい・・・!」
予期していなかったらしく、レイファンに向かってくる男たちにジャンが声を上げた。
それを聞いてか、レイファンが一瞬ジャンリーの方を向き、
「大丈夫よ。」
それだけ言って、微笑んだ。
胸の真ん中目掛けてナイフを突き出してきた男の手を救うように外側へ外し、懐へ飛び込む。
彼女の細い足がアスファルトを踏み割った。攻め手を払われて前のめりになった男の鳩尾に肩からぶち当たって行く。
白目を剥いた男が数m吹き飛んだ。それを見て、二人の男が同時にかかってきた。
一人は鉄パイプ、もう一人は得物を捨てて、素手である。男が最上段から鉄パイプを振り下ろす。
体捌きを駆使して外に避けたレイファンが脇腹に肘撃を叩き込む。
すぐさま振り返るが、その胸倉を素手の男が掴む。男はそのまま力任せに押し込んできたが、彼女はその力のままにその場に倒れこみ、
巴投げの要領で男を投げ飛ばした。
すっかりレイファンに相手を取られてしまったジャンは、彼女の動きに見とれていた。
彼女の太極拳は明らかにその滑らかさが増している。
以前に比べて、彼女らしい前に出て行こうとする攻撃性が、鳴りを潜めたように感じるのだ。
まるで、途切れることなく流れ続け、穏やかな川面から氾濫した濁流へと姿を変える水のような華麗な動きだった。
(あれが、捨己従人てやつか・・・。まさか実戦で使いこなせる奴がいたとはな。)
実際の殴り合いにおいて、飛び掛ってくる相手の勢いに飲まれず、力の方向に従って戦うというのは、
相当な技術を要する上、相手の恐怖に打ち克つ並々ならぬ胆力が必要である。
おそらく、二度にわたるDOAの修羅場が、彼女にこの力を授けたのだろう。
(こりゃあ、今回もうかうかしてらんねーみたいだな。)
最後の男を双按(両手で突き飛ばす技)で吹き飛ばしたレイファンを見ながら、ジャンは微笑した。
*
「あんた、刃物持った男相手に戦ってる女の子見て、助太刀しようとか思わないわけ?」
警察の厄介になると面倒なので、その場を立ち去った二人は通りを歩いていた。
先ほどの立ち回りで、ジャンが手助けしなかったことを、レイファンがなじっている。
「相手が小物だったからよかった様なものの・・・。」
こちらを見ようとしないジャンの横顔を睨みながら、レイファンが膨れっ面でなおも喰らいつく。
「ねえ、聞いてる?」
余りに無反応なのでいい加減彼女はちょっとむかついてきた。
その言葉にジャンが立ち止まり、レイファンに向き直る。
「どうやら腕を上げたようだし、俺の助太刀は無用かと思ったんでな。」
「え?」
いきなりジャンに褒められるとは思っていなかったのか、レイファンは呆けていた。
「これは次の大会に備えて俺も頑張らなきゃならんかな。」
そういうと相変わらず呆けているレイファンに構わずジャンが歩き出した。
それに気づいて、思わずレイファンが声を上げる。
「ジャン!それって・・・。」
その声に振り返ったジャンが、いつか見せた口の端を持ち上げた笑顔で、
「第三回大会、楽しみにしてる。」
それだけ言うと、今度は再び立ち止ることなく、夕闇迫る街に消えていった。
残されたレイファンは、ジャンの言葉の意味に気づいて、一人その場に赤くなっていた。
(あのジャンが、私の力を認めてくれた・・・。)
今まで一度ならず二度までも敗北を喫したその相手から、次も楽しみにしている、だ。
レイファンは飛び上がりたいほどの衝動に駆られた。
(よし、明日の朝からはまた老師と頑張らなきゃ!)
などと、様々考えているうちに彼女はいても立ってもいられなくなり、思わず彼が消えた方に向かって大声で叫んだ。
「見てなさい!今度こそ貴方を倒して見せるわ!」
――三度目の正直、今度こそ私は、あの男を倒して見せるわ。
決意の瞳が、夕闇の街に輝いていた。
FIN